
『計画相談支援』とは障がい福祉サービスの利用を行う時に必要となる計画案を作成、作成した計画が利用者にとって適切であるかを都度確認をして支援を行う行為です。
障がい福祉サービスを利用するにあたり、自治体へ利用申請が必要になり、その際に必ずサービス等利用計画を作成しなければなりません。
サービス等利用計画とは、障がい福祉サービスの利用が決定している方が、地域社会で日常生活を行っていく上で必要となるサービス等を上手く活用するために作成する計画表です。
『計画相談支援』では、このサービス等利用計画を活用し、調整を行ったり、障がい福祉サービスの利用が適切であるかを随時確認していきます。つなごやでは、下記の主な流れで行なっております。
計画相談の流れ
- アセスメント
障がい者の置かれている環境、心身の状況、日常生活の状況といった本人の生活に関わる事項をご本人様の事業所への来所、または家庭訪問により相談支援員が聞き取りします。
- サービス等利用計画案
- 生活に対する意向
- サービスの目的、その達成時期
・総合的な援助の方針
- 解決すべき課題
- サービスの種類、内容、量
- サービス担当者会議
本人、保護者、本人関係者などとサービスの内容や生活に必な支援について確認や、話し合いを行います。
サービス利用計画案の提出。
- 支給決定(市町村)
サービス利用計画案の提出。サービスの種類、内容、量が妥当と認められたら支給決定の運びとなります。障害支援区分、サービスの種類支給量等を記載した障害福祉サービス受給者証、通所受給者証、地域生活支援サービス受給者証が交付されます。
- 事業所との契約・利用
受給者証をサービス事業所に提示し、契約を交わした上でサービス利用をします。
- サービス等利用計画
支給決定されたら「案」の記載のとれた「サービス利用計画」を作成します。「サービス利用計画」が本人、障害福祉サービス事業者の元に届けられます。事業所は届けられたサービス利用計画の内容を踏まえ、各サービス事業所の個別支援計画を作成します。
- 継続サービス利用支援
モニタリングと呼ばれ各事業所などに本人の支援が計画に基づいて滞りなく行われているかなどの聞き取りをします。
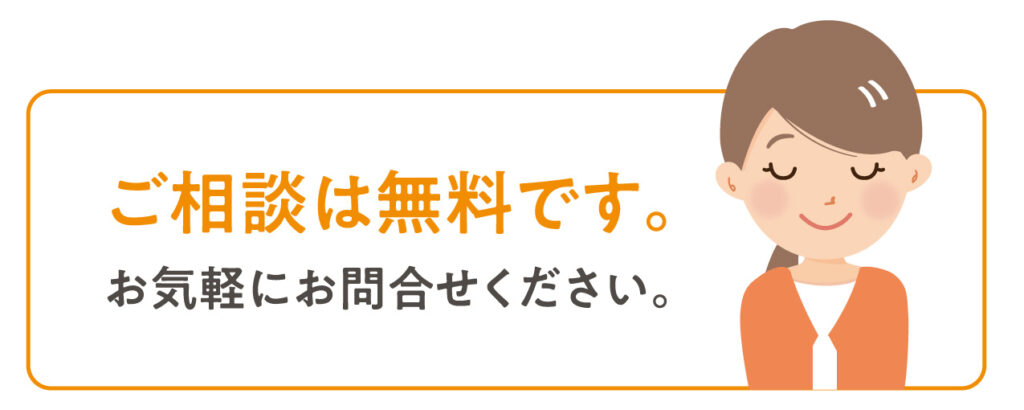
ご相談はこちら
下記の項目をご入力ください。電話でのお問い合わせも受け付けております。

